
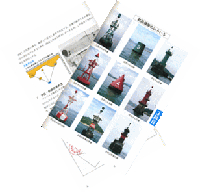
| 教本には、様々な船舶に関するルールやコンパスを使っての進路・位置の求め方、各種標識の説明など内容は盛りだくさん。 |

| たとえば上のような標識は「右げん標識」といい、入港するとき、その右側に障害物があり、その標識の左側に可航水域があることを示している。身近なところでは東扇島西公園の先端付近で、投げ釣り師がターゲットにしているあの標識がこれにあたる。 |
|
|
学科講習はスクールではなく、中央区の区立産業会館で行なわれた。
当日は教本・問題集・練習用ロープを持参してレッツ・ゴー!
朝から夕方までみっちり講習が行なわれるのだが、こんな長時間講習を受けるのは久しぶり。かなり昔に予備校へ行っていた頃を思い出す(笑)
9時15分よりいよいよ講習開始。受講生はこの日11人。歳の頃も若者から年長の方まで様々である。
科目は大きく3科目に分かれており、「小型船舶の船長の心得及び遵守事項」「交通の方法」「運行」という順番であるが、この中でも1科目目は心得的なものなので誰でもすぐにわかるような内容なのだが、2科目から3科目目あたりになると、実際の交通ルールであるとか、灯台や浮標といった海上の標識などなど、初めて聞くことばかりなので覚えるのが大変である。はっきり言って小型船舶の免許を取得するには自動車免許のように教習所に何日も通う必要がないのでその分楽チン(この日の講習を受けたら次回はもう学科試験なのである・笑)なのだが、なにせ下地がないのがちと辛い。
たとえば自動車なら、自動車免許を持っていなくても、赤信号は止まれで青は進めとか、横断歩道は歩行者が歩いて渡るところ、道路わきのスピードが書いてある標識は制限速度、、、といったことを知っているものなのだが、船の場合はほとんどそういった下地がなかったりする。
講習で見るもの聞くことが初めての事柄ばかりで、終始「へぇ〜・へぇ〜」といった感じである(笑)
たとえば、船を操縦していて右舷直前に落水者や障害物を発見した場合、舵をとるのは右か左かといったとき、これが自動車ならば当然左にハンドルを切るほうが良いのだが、小型船舶の場合は右に転舵するというのが正解なのである。
その他にも覚えるのが少々大変なのが「結び」である。結びの王道とも言われる「もやい結び」から「ひとえ結び」「いかり結び」「巻き結び」などなど…
講義の中で当然、結びについてマスターする時間もあり、講師の人が「この中で釣りをされる方はどのくらいいますかぁ〜」という質問に対し、11人中9人が手を挙げた。「釣りを普段されている方は結びは楽勝だと思いますよ〜」と言うのだが、普段せいぜい2種類くらいしか結びを使わず、針とハリスを結ぶのも機械任せの小生にとってはかなりの難関。
他の受講生も結びに手間取っていたが、その中でうまく結びのできないオジサンが「うまく結べないのはこのロープがいけないんだな」と言い出し、講師の人が「というよりも、○○さんご自身の問題だと思いますが・・・」と一蹴される場面もあり、教室内は大爆笑。。
小生も結びにはかなり手間取り、講師に何度もレクチャーを受けた。「普段釣りをしている方は結構飲み込み安いんですけどね〜、あれ、○○さんは釣りするんでしたっけ?」と言われ、「はい…私も一応釣りするんですけど…」と小声で言ったら講師の人は「へっ?」と驚いていた…(笑)
講義の最後に、「試験を受けるまでは問題集が大事になってきます。問題集はしっかりやっておいてください。試験問題はこの問題集の中から出題されます。で、実際に免許を取得したら今度は教本が大切になってきます」と言われた。
「そうかぁ、、とりあえず試験に受かるためには問題集をやって丸暗記するしかないんだな…」
小型船舶は、自動車に比べて免許を取得するのは簡単だが、取得後実践面において何かと大変なものなのかも知れない。小生はそんな感じがした。
次回はいよいよ学科試験。ウン年ぶりの受験勉強の成果は吉と出るか否か…
|


